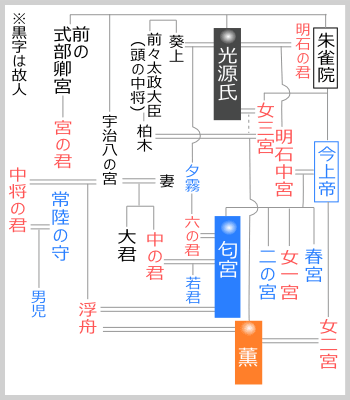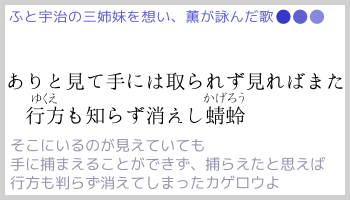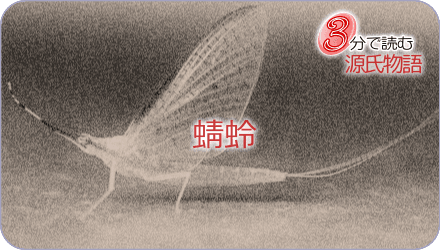浮舟の訃報
浮舟の訃報
宇治では浮舟の姿が見えないので、乳母をはじめとして屋敷中で大騒ぎとなった。しかし事情を知っている女房は、浮舟が悩みぬいた末に宇治川に身を投げたのではないかと察した。
匂宮も何だか胸騒ぎがして宇治に使いを送ってみれば、やはり浮舟が死んだという報告が上がって来る。とても信じられず再度使いを出して顔見知りの女房から話を引き出すが、答えは変わらなかった。せめて亡骸でもあればまだ諦めもつくが、探すあてもない。
世間体もあるので、女房たちはその日のうちに内々でひっそりと葬儀が執り行った。
そのころ女三宮が病に伏せってしまっていたので、薫は石山寺(滋賀県大津市)に籠っていた。浮舟の訃報に驚くが、既に日数を決めて寺籠りしているため、すぐ宇治に向かうわけにもいかない。しかも既に葬儀を済ませたとの報せ。これには薫も大きく不満を感じた。
それにしても宇治と言う土地はなんと不吉な場所なのか。大君の死を招いた場所に浮舟を匿っていたために、彼女は匂宮と通じ、しかもあっけなく死んでしまった。薫は自身の迂闊さを悔やむしかなかった。

匂宮は正気を失ったかのような心地で数日を過ごした。病気で伏せっていることにしてはいるものの、あまりの落胆ぶりに周囲は何事かと気を揉む。
匂宮の不調を見舞う者は引きも切らず、自分だけが無視しているのも拗ねているようでみっともないと思った薫は、夕暮れ時に匂宮を訪ねる。淡々と見舞の口上を述べる薫の姿に、冷徹さと悟りきった達観を見た匂宮だったが、薫も浮舟のことを語るうちに涙を堪え切れなくなった。初めて見る薫の涙に、匂宮も言葉を詰まらせる。
月が改まった。あの折の様子を知る女房を自邸に招いて詳しく話を聞こうと、匂宮は使いを宇治に送った。上洛した女房は仔細を明かし、匂宮と一晩中浮舟のことを語り過ごした。
 浮舟を忘れられず
浮舟を忘れられず
薫もまた宇治へ向かい、女房から匂宮と浮舟の関係まで一切合切を聞き出す。真相を全て知った薫は、遣る瀬無い気持ちで一杯になった。
浮舟の母・中将の君のもとに薫から連絡が行く。娘を失って悲嘆に暮れる彼女を見舞い、まだ幼い浮舟の弟たちの将来の任官についても世話をするつもりだという内容であった。
中将の君はこれまでのいきさつを夫の常陸の守に話しておらず、ここにきてようやく全てをつまびらかにする。常陸の守は権威にめっぽう弱い田舎者なので、今になって継娘の死を惜しく感じて泣くのだった。
四十九日の法要は自然と盛大なものとなった。今上帝の耳にも噂は届き、娘である女二宮への配慮から浮舟の存在を隠していたのだなと、帝も薫を気の毒に感じる。薫も匂宮も悲しみは未だ消えず、匂宮に至っては心の慰めになるかと他の女性に手を出したりもしているようだ。

匂宮の兄・二の宮が式部卿宮になった。姉の女一宮には小宰相の君(こさいしょうのきみ)という女房がおり、匂宮は彼女に関心を抱いていた。楽器の演奏が上手で、機転も利くし美人である。
しかしこれもまた薫に先手を打たれていた。匂宮はどうにか薫から彼女を奪いたいものだとあの手この手で誘うものの、小宰相の君には通用しない。
薫もまたこれほど才気がある女性がどうして宮仕えなどしているのか、いっそ彼女をどこかへ匿っておきたいと思ったりもするが、決して口には出さないのであった。
 気が多い薫
気が多い薫
明石中宮が法要を催し、恙なく終了した。その後片付けの最中は開けっぴろげになって中が丸見えだったため、薫が女一宮の姿を偶然にも見てしまう。その美貌にすっかり夢中になった薫。姉妹なのに彼女と女二宮とは全然似ていない。
自邸に戻った薫は、女一宮が着ていたような薄手の衣装を女二宮に着せてみては、彼女の身代わりとして心の慰めになるかとほくそ笑む。挙句に明石中宮に対して、女二宮が臣下へ降嫁して姉妹と縁が切れたように感じ寂しがっていると嘘まで進言して、女一宮に女二宮宛ての手紙を書くことを勧めるよう求めた。
女一宮から女二宮に手紙が届いた。それを見るとやはり筆跡も見事で心奪われる。そもそも大君さえ生きていれば女二宮を娶らずに彼女だけを愛し続けられたのに。彼女の死によって中の君に懸想し、浮舟を匿い、今度は女一宮に恋心を抱いている。なんと愚かしいことかと自戒する薫。

亡くなった式部卿宮(源氏の異母弟。朝顔の父の桃園式部卿宮や紫の上の父とは別人)の娘が継母に軽んじられていたのを不憫に思った明石中宮が、彼女を引き取った。宮の君(みやのきみ)と呼ばれ、中宮の子女の世話役として奉公する身の上になったものの、もとは春宮に嫁入りさせようかと式部卿宮が考えていた境遇から見れば雲泥の差ゆえに、薫はこの処置に納得がいかなかった。
匂宮は彼女が浮舟と血縁があることから、もしや浮舟に似てはいまいかと別の方向性で宮の君が気になっているようだ。
月が見事な夜。薫は女房たちが集まる部屋に宮の君を訪ねた。同じ皇族でありかつては薫との縁談の話もあった身が、今は女房となりいそいそ奉公しているのを見ると同情を禁じ得ない。と同時に同情だけではない別の感情も生まれてくるのを薫は感じた。
それでもやはり大君や中の君、浮舟をふと思い出すのだ。